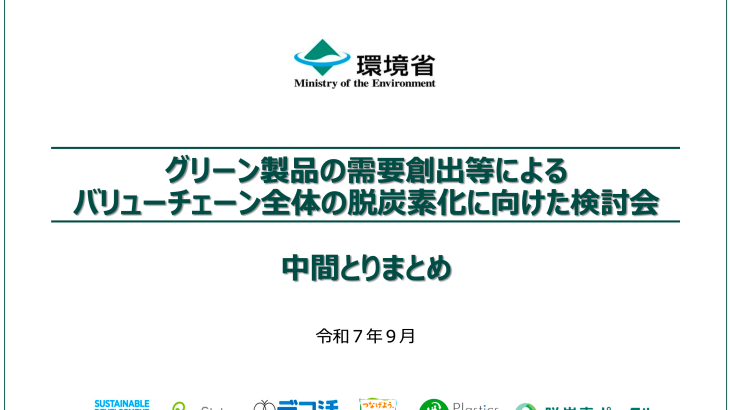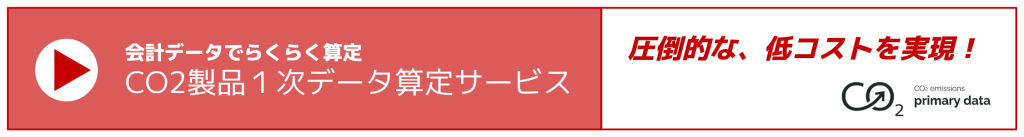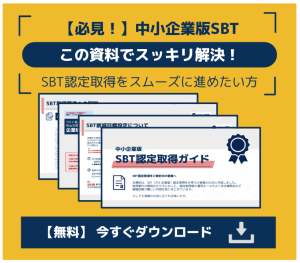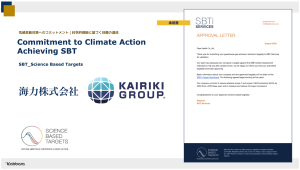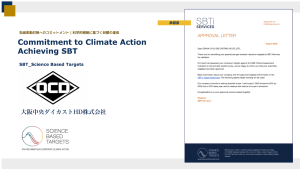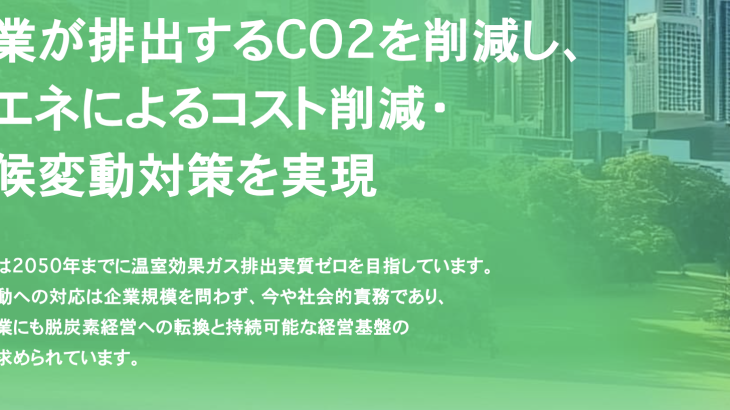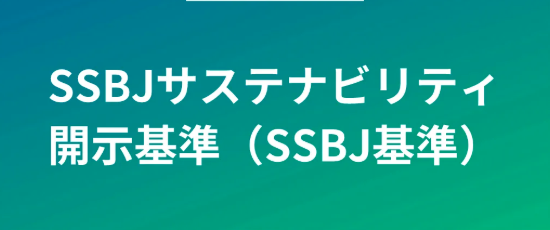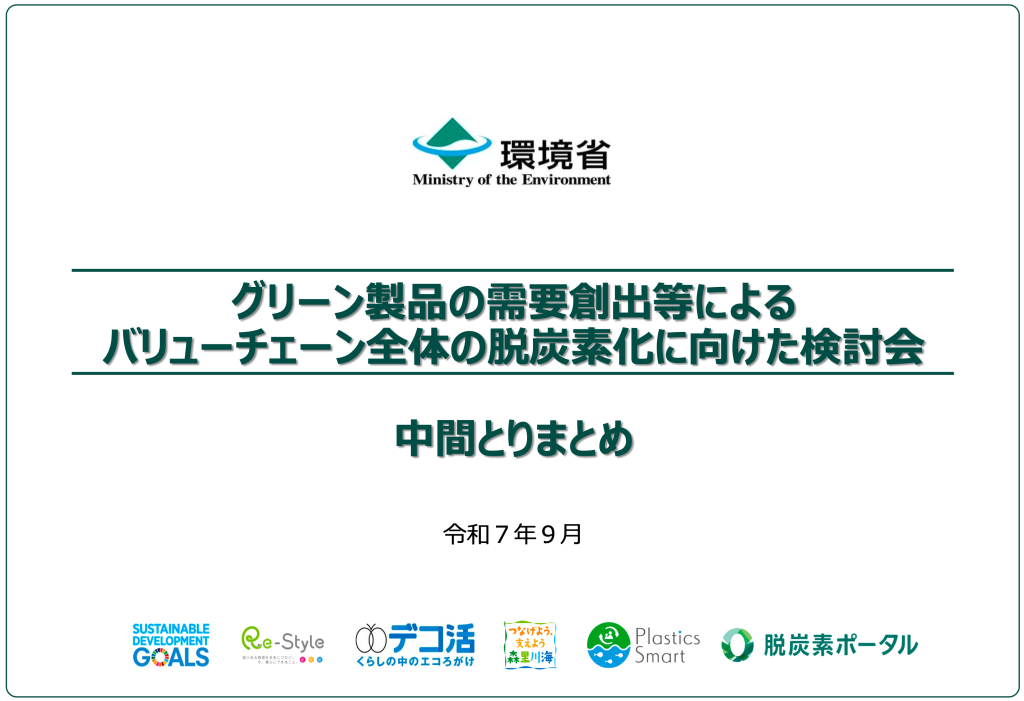
はじめに
本日は、グリーン製品の需要創出等によるバリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会の中間とりまとめをわかりやすく整理し、お届けします 。2050年ネット・ゼロという国家目標達成に向け、企業活動におけるCO2排出削減は待ったなしの状況です 。この報告書は、多くの企業が直面する脱炭素化の課題を浮き彫りにし、その解決に向けた国の具体的な方針を示す、いわば未来のビジネス戦略の羅針盤です。この記事では、専門的でボリュームのある報告書の中から、すべてのビジネスパーソンが知っておくべき (核心)を4つのポイントに絞って徹底解説します。
この記事のサマリー
- グリーン製品の需要創出には、「最終需要の喚起」「企業間連携の強化」「中小企業の脱炭素経営浸透」という3つの課題がある 。
- 消費者は環境配慮製品への意欲は高いが、「どれが環境に良いかわからない」ことが購入の最大の障壁となっている 。
- 製品のCO2排出量の約8割はサプライチェーンで発生しており 、データ連携の遅れや中小企業のリソース不足が削減のボトルネックとなっている。
- 政府は「需要喚起」「連携推進」「サプライヤー支援」「地域支援」の4つの方向性で施策を推進し、企業の取り組みを後押しする 。
- 特に、消費者がグリーン製品を選ぶ市場を創出する「最終需要の喚起」が最優先課題であり、将来的には制度的措置の導入も視野に入れている 。
なぜ脱炭素は進まない?日本企業が直面する「3つの大きな壁」

環境省の報告書では、バリューチェーン全体の脱炭素化を進める上で、日本市場全体が3つの大きな課題に直面していると分析しています 。これらは個別の問題ではなく、互いに深く関連し合っています。
- 課題A:グリーン製品・サービスへの最終需要の喚起
環境に配慮した製品(グリーン製品)を作っても、消費者に選ばれず、市場が育たない問題です。最終的な出口である消費者需要が盛り上がらなければ、企業は脱炭素投資に踏み切れません。 - 課題B:バリューチェーン内企業間の連携強化
製品のCO2排出量の多くは、自社ではなく原材料の調達や部品製造といったサプライチェーン上で発生します。しかし、企業間で排出量データなどを共有・連携する仕組みが未整備で、サプライチェーン全体での削減が進みにくい状況です。 - 課題C:中堅・中小企業における脱炭素経営の浸透・定着
サプライチェーンを支える多くの中小企業では、人材や資金、ノウハウ不足から脱炭素経営への取り組みが遅れがちです 。大企業からの働きかけも届きにくく、バリューチェーン全体のボトルネックとなっています 。
企業の規模や業種によって直面する課題の比重は異なりますが、この3つの壁を乗り越えない限り、日本全体の脱炭素化は実現しません。次の章から、それぞれの課題の深層と、その解決策を具体的に見ていきましょう。
【課題A】買いたいけど選べない。消費者の本音とグリーン市場の現状

グリーン製品が普及しない最大の要因は、消費者の環境意識が低いからではありません。報告書で引用されている調査データは、衝撃的な事実を示しています。
実は、消費者の63%(「強くそう思う」11%+「そう思う」52%)が「今後の買い物で環境負荷の少ない商品を買いたい」と回答しています 。しかし、実際に行動に移せている人はごく一部です。なぜなら、購入に踏み出せない理由のトップが「どの商品が環境負荷の少ない商品なのか、よくわからないから」(52%)だからです 。
つまり、市場には「環境に良い製品を選びたい」という潜在的な需要が確実に存在するにもかかわらず、企業からの情報提供が不足しているために、その需要が「死んで」しまっているのです。この「情報の非対称性」が、グリーン市場の成長を阻む根本的な原因であると報告書は指摘しています。
この問題を解決するためには、メーカー単独の努力では不十分です。消費者に最も身近な接点である小売店と連携し、店頭で製品の環境価値を分かりやすく伝える仕組みが不可欠です 。さらに、国が主導して信頼できる評価基準や表示ラベルを整備することで、消費者が安心して製品を選べる環境を整えることが急務とされています 。消費者の「わからない」を「これならわかる」に変えることこそ、需要を喚起する第一歩なのです。
【課題B/C】一社では限界!サプライチェーン連携と中小企業の課題
多くの企業が自社の省エネ(Scope1, 2)に懸命に取り組んでいますが、報告書はサプライチェーン排出量(Scope3)の削減なくして目標達成は不可能だと強調しています 。消費者向け最終製品を生産する業種では、総排出量の約8割(電機機器77%~日用品90%)がScope3(上流)で発生しているというデータもあり、その重要性は明らかです 。
しかし、サプライチェーン全体での削減を進めるには、企業間連携、特にバリューチェーンを支える中小企業の協力が不可欠であり、そこには深刻な課題が存在します。

課題B:進まない企業間連携】 サプライチェーン全体での排出量を正確に把握するには、各サプライヤーから実際の活動に基づいた「1次データ」を提供してもらう必要があります。しかし、「業界ごとに算定ルールがバラバラで対応しきれない」「企業秘密であるデータをどこまで開示すればいいのか」といった懸念から、データ連携は思うように進んでいません 。その結果、多くの企業が一般的な係数を用いた「2次データ」で算定せざるを得ず、サプライヤーの個別の削減努力が評価に反映されにくいという問題が生じています 。
【課題C:取り残される中小企業】 日本のCO2排出量のうち、中小企業が占める割合は最大で約2割に達し、無視できない存在です 。しかし、多くの中小企業経営者は、人材・資金・ノウハウの不足に加え、「脱炭素に取り組まなくても、今のところ取引に影響はない」と感じており、将来的な経営リスクへの認識が不十分なのが現状です 。大企業からのエンゲージメントも届きにくく、脱炭素化の必要性を感じる機会自体が少ないという課題も指摘されています 。
これらの課題を放置すれば、日本の産業全体の競争力が失われかねません。サプライチェーンの川上から川下まで、切れ目ない支援と連携の仕組みづくりが求められています。
未来への処方箋:政府が示す具体的な4つの支援策
これまで見てきた複雑な課題に対し、報告書は政府が今後取り組むべき施策の方向性を4つに整理して提示しています 。これは、企業が脱炭素化を進める上で活用できる支援策の全体像でもあります。

① 政府・企業・消費者におけるグリーン製品需要の喚起(施策A)
これが最も優先順位の高い施策と位置づけられています 。具体的には、信頼できる「グリーン製品の評価・表示スキーム」を創設し、消費者が選びやすい環境を整備します 。また、メーカーと小売が連携した販売モデル事業を支援し、効果的な価値の伝え方を横展開していきます 。
② バリューチェーン内企業間の連携推進(施策B)
企業間のデータ連携を円滑にするため、業界ごとのデータベース構築などを支援します 。また、サプライチェーン全体で優れた脱炭素の取り組みを行う企業を表彰するなど、連携の価値を「見える化」し、先進事例を奨励します 。
③ 代表企業起点のサプライヤー・エンゲージメントの推進(施策C-1)
バリューチェーンの中心となる大企業が、サプライヤーである中小企業の脱炭素化を支援する取り組みを後押しします 。例えば、大企業と中小企業が連携して省CO2設備を導入する際の補助金を拡充したり 、大企業の信用力を活用して中小企業が再生可能エネルギーを導入しやすくする新たな金融スキームの創出を支援したりします 。
④ 地域単位での中堅・中小企業の脱炭素支援(施策C-2)
地域金融機関や商工会議所、自治体などが連携して中小企業を支援する「地域ぐるみ」の支援体制の構築を全国で推進します 。専門家派遣や相談窓口の設置など、中小企業が気軽に脱炭素経営の第一歩を踏み出せる環境を整えます 。
これらの施策は、短期的なモデル事業から、将来的な制度的措置までを見据えた、包括的なパッケージとなっています。
まとめ
今回解説した「中間とりまとめ」は、バリューチェーン全体の脱炭素化が、単なる環境問題ではなく、新たな需要を創出し、産業競争力を強化するための国家戦略であることを明確に示しています。
報告書の結論として特に強調されているのは、何よりもまず「最終需要の喚起(施策A)」に最優先で取り組むべきだという点です 。消費者がグリーン製品を積極的に選ぶ市場が生まれれば、企業は経済合理性に基づいて、自ずとサプライチェーン連携や中小企業の脱炭素化を進めるようになるからです。
しかし、消費者の意識変革だけに頼るには限界があります。そのため、将来的には優れた環境価値を持つ製品が市場で正当に評価され、調達・購入されるような
税制や規制を含む「制度的措置」の導入が必要不可欠であると提言されています 。この報告書は、すべての企業に対し、未来の市場ルールを先読みし、今すぐ行動を起こすことの重要性を強く訴えかけているのです。
製品1次データ算定サービスはこちらからどうぞ