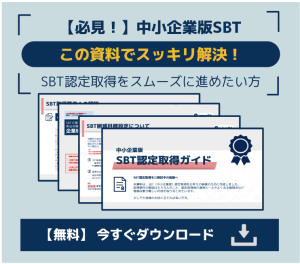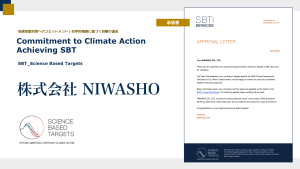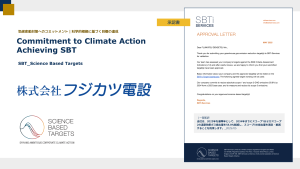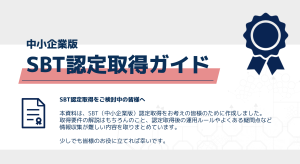地球温暖化が深刻化する中、各国は温室効果ガスの排出削減に向けた取り組みを加速させています。その中でも注目されているのが「カーボンプライシング(炭素の価格付け)」です。カーボンプライシングは、炭素排出の外部コスト(環境への損害など)を経済活動の主体に内部化させるための主要な手段です。これには主に「炭素税」と「排出量取引制度(ETS)」の2つの形態があります。
今回は、特に炭素税に焦点を当てつつ、関連する排出量取引制度や国際的な動向についても触れながら、その仕組み、導入国、各国の税率比較、メリット・デメリット、そして今後の展望についてご紹介します。
カーボンプライシングの主な仕組み
- 炭素税 (Carbon Tax):
炭素税は、化石燃料の炭素含有量や、それらから排出される温室効果ガスの量に直接価格を設定するものです。企業や個人は、排出量に応じて税金を支払うことで、排出削減へのインセンティブが生まれます。炭素税の利点は、価格が固定されるため予見性が高いこと、そして比較的実施が容易である点です。しかし、排出削減量そのものは保証されません。 - 排出量取引制度 (Emissions Trading System – ETS):
ETS(キャップ・アンド・トレード制度とも呼ばれる)は、まず温室効果ガス排出量の上限(キャップ)を設定します。その範囲内で排出枠(アローワンス)が企業などに割り当てられたり、競売にかけられたりします。排出枠が余った企業は、不足している企業に売却でき、これにより市場で炭素価格が形成されます。ETSは総排出量を確実にキャップ内に抑えることができますが、炭素価格は市場の需給によって変動します。
これら二つの制度は相互に排他的ではなく、異なるセクターを対象に併用されることもあります。
各国の炭素税・ETS導入状況
各国の炭素税・ETS導入状況 炭素税やETSを導入している国・地域は世界中に広がっています。ヨーロッパでは、スウェーデンやフィンランドなどが早くから炭素税を導入しているほか、EU全体では大規模なEU-ETSが機能しています。北米では、カナダが州ごと及び連邦レベルでカーボンプライシングを導入しており、アメリカでも一部の州(例:カリフォルニア州のETS)で導入が進んでいます。
世界銀行の「State and Trends of Carbon Pricing 2024」報告によると、2023年には炭素価格による収益が過去最高の1040億ドルに達しました。現在、世界で75のカーボンプライシング制度が稼働しており、世界の温室効果ガス排出量の約24%をカバーしています。しかし、パリ協定の目標達成に必要な価格水準でカバーされている排出量は、世界の排出量の1%未満に留まっています。ブラジル、インド、チリ、コロンビア、トゥルキエといった主要な中所得国も炭素価格設定の導入で進展を見せています。
以下は、炭素税率が高い国や注目すべき制度の例と、近年の動向です。

スウェーデン:
早くから炭素税を導入し、税率は世界最高水準です。2025年の税率は1トンあたり1,510スウェーデンクローナ(約134ユーロ)に達する見込みです。スウェーデンの炭素税はEU ETSと並行して機能し、現在ではスウェーデンの化石燃料由来のCO2排出量の95%以上がこれらによってカバーされています。
スイス:
炭素税を導入しており、税収の約3分の2は企業や市民に還元されています(例:健康保険料の軽減)。
アイルランド:
2024年の炭素税率は1トンあたり56.00ユーロです。
ドイツ:
輸送・暖房セクター向けの国内排出量取引制度(nEHS)を通じて炭素価格を設定しており、2024年の固定価格は1トンあたり45ユーロです。
カナダ:
連邦レベルの燃料課徴金制度と州ごとの制度があります。連邦制度では、ガソリンに対する炭素税率は2024年4月1日から2025年3月31日まで1リットルあたり0.1761ドルです。カナダでは、炭素税収の大部分を「カナダ炭素リベート」として家計に直接還元する方針を取っています。しかし、2025年4月1日より、連邦政府は消費者向け燃料課徴金を停止し、州や準州に対する消費者向け炭素価格設定の義務付けも解除する規制を制定しました。この政策変更は、インフレへの一時的な下方圧力として作用すると分析されています。
EU ETS:
世界最大の排出量取引制度で、発電所や大規模工場、航空業界などを対象としています。2024年には海運セクターも段階的に組み込まれ始めています。
炭素税収の活用方法
炭素税収の活用方法 炭素税やETSから得られる収益の使途は国や地域によって様々です。主な活用方法としては、
- 一般財源への組み入れ: アイルランドなどでは、税収は政府の一般歳入として扱われます。
- 特定目的への支出:
- 環境関連プロジェクト: 低炭素プロジェクトへの投資(全体の約46%の収益がこの目的で使用される例あり)。カナダのケベック州では、「グリーンファンド」の収益の3分の2が州最大の排出源である運輸セクター(公共交通や電化など)に充てられています。
- 低所得者層への配慮・還付: 税負担の逆進性を緩和するため、低所得世帯への補償や、市民全体への均一な還付(カーボンディビデンド)が行われることがあります。スイスでは税収の3分の2が市民や企業に還元されます。カナダも「カナダ炭素リベート」で家計に還元しています。
- 他の税の減税: スウェーデンでは、炭素税導入と並行して所得税や法人税の引き下げが行われました。
- 債務削減など
効果的な炭素税制の設計には、税収の使途を透明化し、国民の理解と支持を得ることが重要です。
日本における炭素税の実態と今後の展望
日本では「地球温暖化対策のための税」という名称で、2012年10月から導入されています。これは石油石炭税に上乗せする形で、二酸化炭素の排出量に応じて課税される仕組みです。具体的な税率は、二酸化炭素排出量1トンあたり289円で、国際的に見ると非常に低い水準にあります。 導入当初は、経済への影響を抑えるために低い税率からスタートし、段階的に引き上げられてきました。この税収は、省エネルギー対策の推進、再生可能エネルギーの導入支援、森林整備、国際的な温暖化対策への貢献などに使われています。 日本の炭素税は税率が低いため、その排出削減効果については議論があります。
新たな動きとして、日本ではGX-ETS(グリーントランスフォーメーション排出量取引制度)の導入が進められており、2023年度から第1フェーズとして自主的な参加が始まり、2026年度からは本格稼働(発電事業者への有償オークション導入)が予定されています。さらに、2028年度からは化石燃料賦課金(炭素に対する賦課金)の導入も検討されています。
炭素税導入のメリットとデメリット・課題
メリット
- 温室効果ガスの排出削減を促進できる(「汚染者負担の原則」の適用)。
- 再生可能エネルギーや省エネ技術の開発・導入を促進できる。
- 企業や個人の行動変容を促す経済的インセンティブとなる。
- 税収を環境対策、社会保障、減税などに活用できる。
デメリット・課題
- 経済的負担の増加と逆進性: 企業のコスト増が物価上昇につながり、特に低所得者層への負担が相対的に重くなる可能性があります(逆進性)。これを緩和するための税収還付策が重要です。
- 国際競争力への影響と炭素リーケージ: 炭素税を導入した国の企業が、導入していない国の企業に対して競争上不利になる可能性があります。また、排出集約型の産業が規制の緩い国へ移転し、結果として世界の総排出量が減少しない「炭素リーケージ」のリスクがあります。
- 排出削減効果の不確実性(炭素税の場合): 税率が低い場合、十分な排出削減効果が得られない可能性があります。
- 政治的受容性: 新たな税負担に対する国民や産業界からの反対により、導入や税率引き上げが困難な場合があります。
- 制度設計の複雑さ: 対象範囲、税率設定、免除措置、税収使途など、制度設計には多くの論点があります。
- 他の温室効果ガスへの対応: 炭素税は主にCO2を対象とし、メタンなど他の強力な温室効果ガスの排出(農業、廃棄物などから)は直接カバーしにくい場合があります。
国際的な動向:カーボンボーダーアジャストメントメカニズム (CBAM)
炭素リーケージへの対策や、国内の気候変動対策の有効性を確保する観点から、「カーボンボーダーアジャストメントメカニズム(CBAM:炭素国境調整措置)」の導入が進んでいます。 CBAMは、輸入品に対して、その製造過程で排出された炭素量に基づいて価格を課すものです。これにより、国内製品と同等の炭素コストを輸入品にも負わせることを目指します。
- EUのCBAM: 2023年10月から移行期間に入り、対象となる輸入品(セメント、鉄鋼、アルミニウム、肥料、電力、水素など)の輸入者に対して、製品に内包される排出量の報告義務が課されています。2026年から本格導入され、輸入者はCBAM証書を購入・提出する必要が生じます。このCBAM証書の価格は、EU-ETSの炭素価格に連動します。EU域外で既に炭素価格が支払われている場合は、その分が控除されます。
- 英国のCBAM: 2027年1月1日から導入予定で、鉄鋼、アルミニウム、肥料、水素、セメント、セラミックス、ガラスなどが対象となる見込みです。こちらも、輸入品に内包される直接・間接排出量が対象となり、海外で支払われた炭素価格は控除可能です。
CBAMは、世界的なカーボンプライシングの公平性を高める可能性がありますが、途上国からの反発や国際貿易ルールとの整合性など、課題も指摘されています。
今後のカーボンプライシング
今後、世界各国はパリ協定の目標達成に向けて、炭素税やETSの導入・強化を進めていくことが予想されます。電力や工業といった従来のセクターに加え、航空、海運、廃棄物といった新しいセクターでも炭素価格の導入が検討されるケースが増えています。 また、各国間の制度の連携や、国際的な枠組みの中でカーボンプライシング制度を構築していくことも重要です。CBAMの動きは、こうした国際的な整合性を求める圧力とも言えます。 日本でもSBT認定の取得をはじめとして脱炭素経営化の流れが加速しています。諸外国と比較すると非常に低い炭素税率の日本ですが、GX-ETSの本格稼働や化石燃料賦課金の導入など、カーボンプライシング強化の動きは具体化しつつあります。より効果的な温暖化対策のためには、これらの制度を適切に設計・運用し、他の政策(規制、補助金など)と効果的に組み合わせることが不可欠です。