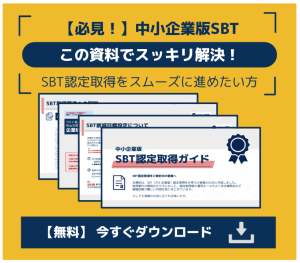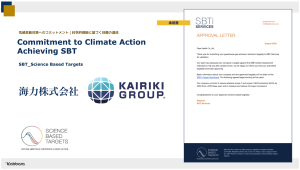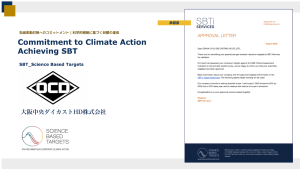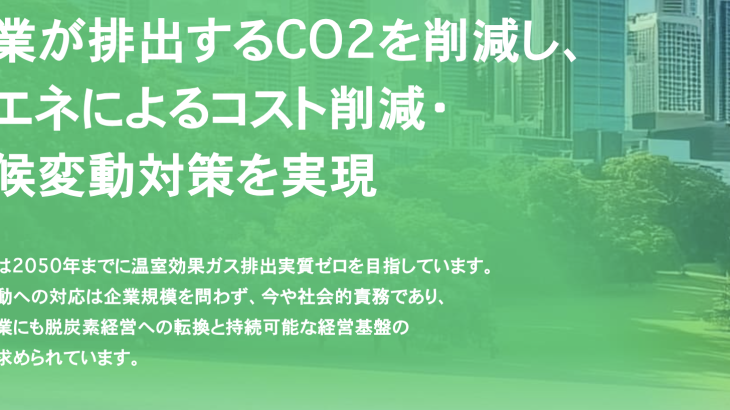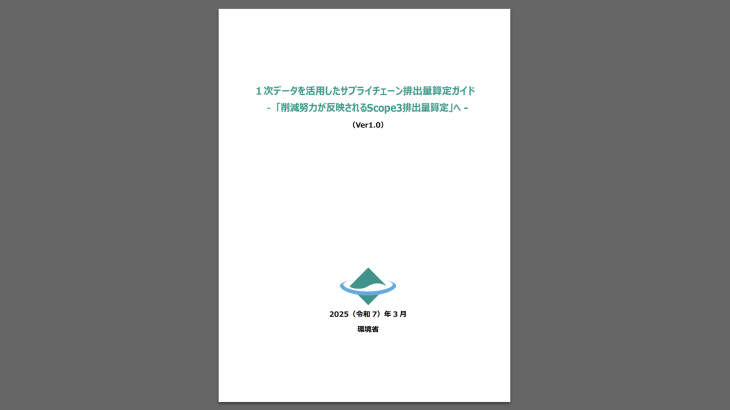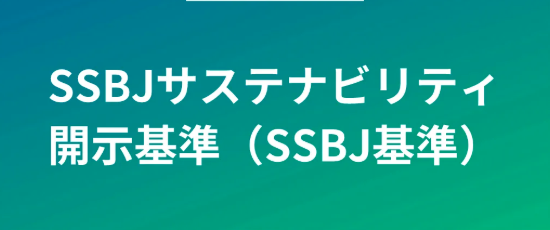2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、社会全体の脱炭素化が加速しています。中小企業もこの変化の影響を受けており、CO2排出量削減の要請やエネルギーコスト高騰といった課題に直面しています。
脱炭素への取り組みはリスクだけでなく、生産性向上、コスト削減、企業価値向上、新たなビジネスチャンスにつながる機会でもあります。国も中小企業の挑戦を支援するため、様々な補助金制度を用意しています。
この記事では、2025年度に中小企業が活用できるカーボンニュートラル関連の補助金について解説します。補助金の最新情報、申請のコツ、注意点などを分かりやすく紹介し、企業の持続的な成長をサポートします。
サマリー
- 中小企業にとって、カーボンニュートラルへの取り組みは経営戦略上重要であり、コスト削減や企業価値向上、新たなビジネスチャンスにつながる可能性がある。
- 2025年度も、省エネ設備導入や事業再構築などを支援する様々な補助金制度が用意されている。
- 補助金の採択には、事業計画書の作成が重要であり、申請には専門家の支援や商工会議所・金融機関への相談も有効である。
おすすめ関連記事
→SBT取得で企業価値向上:投資家・金融機関からの評価を高める
【2025年度版】目的別!中小企業が使える主要カーボンニュートラル補助金
2025年度も、経済産業省や環境省を中心に、中小企業の脱炭素化を支援する多様な補助金が用意されています。ここでは、企業の目的別に代表的な補助金を紹介します。
(注) 2025年度の公募要領は発表前のものも含まれるため、2024年度の実績や予算案をもとに解説しています。申請を検討する際は、必ず各省庁や執行団体のウェブサイトで最新の公募要領をご確認ください。
A. 省エネルギー設備への更新をしたい【省エネ補助金】
最も多くの企業が活用しやすいのが、既存設備をエネルギー効率の高いものへ更新する際の費用を補助する制度です。
省エネルギー投資促進支援事業費補助金
https://sii.or.jp/setsubi06r/
- 管轄: 経済産業省(執行団体:一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII))
- 目的: 工場・事業場におけるエネルギー効率の改善。
- 対象設備: 高効率空調、産業用ヒートポンプ、業務用給湯器、高効率コージェネレーション、高性能ボイラ、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータなど、あらかじめ定められた高性能な省エネ設備。
- 補助率・上限額(目安):
- (A)先進設備・システム: 補助率 中小企業 2/3以内、上限 15億円/年度
- (B)オーダーメイド型設備: 補助率 中小企業 1/2以内、上限 15億円/年度
- (C)指定設備導入: 補助率 1/3以内、補助金上限は設備により異なる。
ポイント: 非常に人気の高い補助金で、公募期間も比較的短いため、事前の準備が鍵となります。導入する設備が要件を満たすか、省エネ計算が必要かなど、専門家のアドバイスを受けながら進めるのが賢明です。2025年も複数回の公募が予想されます。
B. 革新的な製品開発や生産プロセス改善と合わせて脱炭素に取り組みたい【ものづくり補助金】
新製品・サービスの開発や生産性向上のための設備投資を支援する補助金ですが、脱炭素に資する取り組みには特別な枠が設けられています。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(グリーン枠)
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
- 管轄: 中小企業庁
- 目的: 温室効果ガス排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発、または炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援。
- 補助率・上限額(目安):
- エントリー類型: 補助率 2/3、補助上限 750万円~1,250万円
- スタンダード類型: 補助率 2/3、補助上限 1,000万円~2,500万円
- アドバンス類型: 補助率 2/3、補助上限 1,250万円~4,000万円
- ※従業員数や賃上げ目標により上限額が変動します。
- ポイント: 単なる省エネ設備の導入だけでなく、「炭素生産性(付加価値額 / CO2排出量)を年率平均1%以上向上させる」事業計画が必須です。自社の強みを活かした生産性向上と脱炭素を両立させる、戦略的な計画策定が求められます。
C. 思い切った事業転換で脱炭素分野に挑戦したい【事業再構築補助金】
ポストコロナを見据え、中小企業の思い切った事業再構築を支援する補助金です。成長分野であるグリーン分野への挑戦を後押しします。
事業再構築補助金(グリーン成長枠)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf
- 管轄: 中小企業庁
- 目的: グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題解決に資する取り組みに関連する、大きな事業転換を支援。
- 対象分野の例: 洋上風力、太陽光、水素、自動車・蓄電池、半導体・情報通信、食料・農林水産業など。
- 補助率・上限額(目安):
- エントリー類型: 中小企業 1/2(賃上げで2/3)、補助上限 4,000万円~8,000万円
- スタンダード類型: 中小企業 1/2(賃上げで2/3)、補助上限 1億円~1.5億円
- ※従業員数により上限額が変動します。
ポイント: 補助額が大きい分、要件も厳しく、事業終了後3~5年で付加価値額を年率平均4.0%以上増加させるなどの高い成長が求められます。全く新しい分野への挑戦となるため、綿密な市場調査と実現可能性の高い事業計画が不可欠です。
D. CO2排出量を大幅に削減する大規模な設備改修をしたい【SHIFT事業】
工場や事業場全体で、CO2排出量を大幅に削減するための設備改修を支援する、環境省の補助金です。
工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)
https://shift.env.go.jp/
- 管轄: 環境省
- 目的: 既存設備を省CO2型の設備・システムに改修し、工場・事業場単位でCO2排出量を大幅に削減する取り組みを支援。
- 補助率・上限額(目安):
- 省CO2型システムへの改修支援: 補助率 1/3以内、補助上限 1億円
- ※CO2削減量に応じて上限額が変わる場合があります。
- ポイント: 「主要なシステム系統で年間CO2排出量30%以上削減」など、高い削減目標が求められます。電化や燃料転換を伴わない、単なる高効率更新は対象外となるなど、要件が詳細に定められています。エネルギー診断などを活用し、自社の排出状況を正確に把握した上での計画策定が必要です。
E. 自社で使う電気を太陽光発電でまかないたい
再生可能エネルギーの導入もカーボンニュートラルの重要な柱です。特に自家消費型の太陽光発電は、電気代削減と環境貢献を両立できるため注目されています。
需要家主導による太陽光発電導入促進補助金など
https://www.env.go.jp/earth/post_93.html
- 管轄: 環境省
- 目的: 企業の敷地内(オンサイト)や敷地外(オフサイト)に自家消費を目的とした太陽光発電設備や蓄電池を導入する取り組みを支援。
- ポイント: 補助金の名称や内容は年度によって変動することが多いですが、自家消費型太陽光発電への支援は継続される見込みです。「FIT/FIP制度(売電を主目的とする制度)の認定を受けないこと」「発電電力の50%以上を自家消費すること」などが一般的な要件となります。PPAモデル(第三者が設備を設置・保有し、企業は電気を購入するモデル)を活用する場合でも、補助金の対象となるケースがあります。
成功の鍵を握る「事業計画書」のポイント
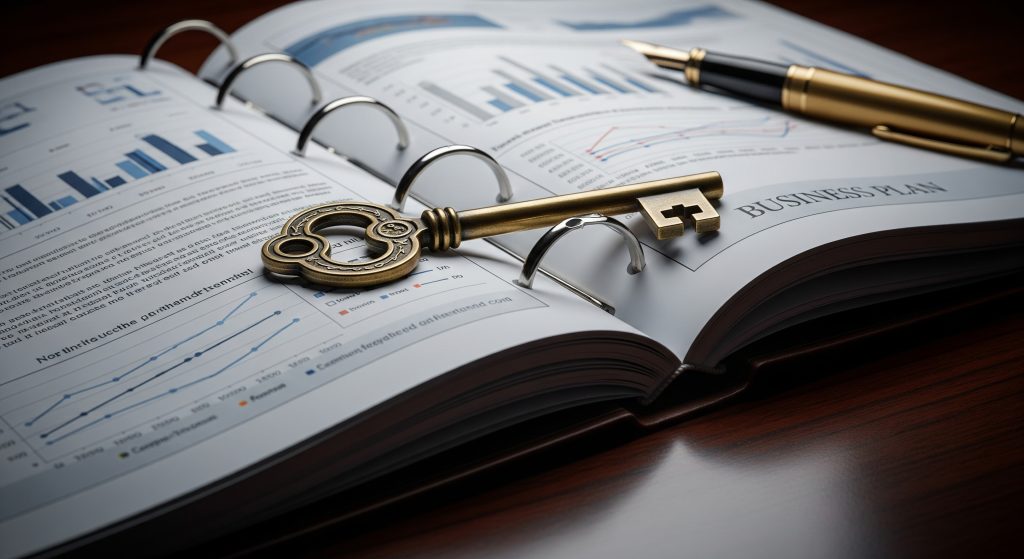
審査員は、数多くの申請書に目を通します。その中で採択を勝ち取るためには、以下の点を意識した事業計画書を作成することが不可欠です。
① 補助金の「趣旨」を理解する
各補助金には、「なぜ国がこの事業にお金を出すのか」という明確な目的があります。公募要領の冒頭に書かれている「事業目的」や「背景」を熟読し、自社の計画がその趣旨にいかに合致しているかをアピールしましょう。例えば、ものづくり補助金であれば「生産性向上」、SHIFT事業であれば「CO2の大幅削減」というテーマから外れた計画では評価されません。
② 自社の課題を明確にし、ストーリーを描く
「なぜ、今この投資が必要なのか?」を説得力をもって説明することが重要です。
- 現状と課題: 自社が直面している具体的な課題(例:旧式設備のエネルギー効率が悪くコストを圧迫している、取引先から環境対応を求められている、など)を数値データを用いて示します。
- 課題解決策: その課題を解決するために、なぜこの補助事業(設備の導入など)が必要不可欠なのかを論理的に説明します。
- 事業後の未来: 補助事業を実施することで、自社の課題が解決され、どのような成長(売上向上、コスト削減、競争力強化)が見込めるのか、明るい未来像を具体的に描きます。
この「課題 → 解決策 → 未来」という一貫したストーリーが、審査員の共感を呼びます。
③ 定量的・具体的な数値目標を掲げる
「省エネを頑張ります」「CO2を削減します」といった曖昧な表現では評価されません。
- CO2削減効果: 「高効率ボイラーの導入により、年間CO2排出量を〇〇t-CO2(〇〇%)削減する」
- 生産性向上: 「新設備の導入により、製品Aの生産時間が〇〇%短縮され、生産性が〇〇%向上する」
- コスト削減効果: 「エネルギー使用量が年間〇〇kWh削減されることで、電気代が年間〇〇万円削減される見込み」
このように、導入する設備の効果を計算し、具体的な数値目標として示すことが極めて重要です。設備のメーカーや販売代理店に協力を依頼し、算出根拠となる資料を添付すると、計画の信頼性が格段に高まります。
④ 加点項目を確実に取得する
多くの補助金には、特定の要件を満たすことで審査上有利になる「加点項目」が設定されています。「パートナーシップ構築宣言」の登録、「賃上げ計画」の策定、「経営革新計画」の承認取得など、比較的取り組みやすい項目も多くあります。公募要領を隅々まで確認し、取得できる加点項目はすべて狙いにいきましょう。これが採択の当落線上を分けることもあります。
⑤ 専門家の力を借りる
事業計画書の作成には専門的な知識が求められます。自社だけでの作成に不安がある場合は、中小企業診断士、行政書士、コンサルティング会社など、補助金申請支援の実績が豊富な専門家に相談するのも有効な手段です。費用はかかりますが、採択の可能性を高め、事業計画そのものをブラッシュアップできるメリットは大きいでしょう。
【失敗しないために】補助金活用の注意点
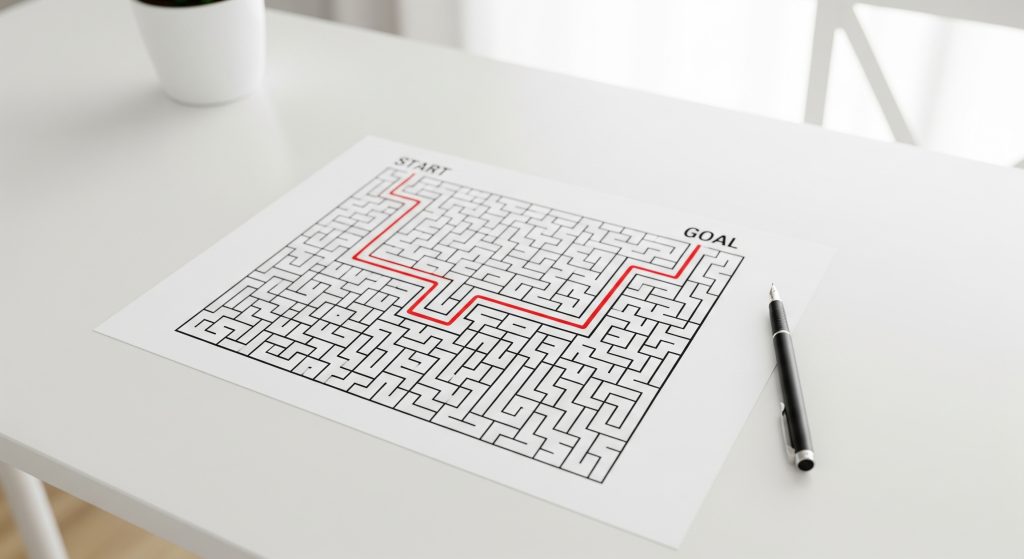
- 補助金は「後払い」が原則!資金繰りに注意
最も重要な注意点です。設備投資などの費用は、まず自社で全額を支払う必要があります。補助金が振り込まれるのは、事業完了後の実績報告と確定検査が終わった後、つまり数ヶ月から1年以上先になることもあります。この間の資金繰りをどうするか、金融機関からのつなぎ融資なども含めて、事前に計画を立てておかないと、黒字倒産のリスクさえあります。 - 「交付決定前」の契約・発注は絶対NG
採択の連絡を受けても、まだ安心はできません。正式な「交付決定通知」を受け取る前に、設備メーカーと契約したり、発注したりすると、その経費は補助対象外となります。フライングは絶対にやめましょう。 - 計画変更には「事前承認」が必要
事業を進める中で、導入する設備の型番が変わったり、金額が変更になったりすることはあり得ます。しかし、申請した計画からの変更には、原則として事務局への事前申請と承認が必要です。軽微な変更なら事後報告で済む場合もありますが、自己判断せず、必ず事務局に相談・確認する癖をつけましょう。 - 補助対象経費の範囲を正確に理解する
補助金の対象となる経費は、公募要領で厳密に定められています。「設備本体価格」は対象でも、「設置工事費」や「運搬費」は対象外、といったケースもあります。また、消費税は原則として補助対象外です。見積もりを取る段階で、どの経費が補助対象になるのかを明確に区分しておく必要があります。汎用性が高く、他の目的にも使用できるもの(パソコン、スマートフォン、車両など)は対象外となることがほとんどです。 - 書類の保管と事業化状況報告の義務
補助事業に関する書類(見積書、契約書、請求書、帳簿など)は、事業完了後も5年間の保管が義務付けられています。また、事業完了後の数年間、補助金によってどのような成果(売上、利益、CO2削減量など)が出たかを報告する「事業化状況報告」を毎年提出する必要があります。これを怠ると、補助金の返還を求められる可能性もあるため、誠実に対応しましょう。
まとめ
2025年、中小企業を取り巻く環境は、エネルギー価格の高騰やサプライチェーンからの脱炭素要請など、厳しさを増す一方で、大きな変革のチャンスも内包しています。カーボンニュートラルへの取り組みは、もはや社会貢献活動ではなく、企業の競争力を高め、持続的な成長を達成するための必須の経営戦略です。
この記事を参考に、まずは自社がどの補助金の対象となり得るのかを検討し、公募要領の情報を集めることから始めてみてください。必要であれば、中小企業診断士や地域の商工会議所、金融機関といった専門家の力も借りながら、戦略的に準備を進めましょう。
カーボンニュートラルという大きな潮流を、コストではなくチャンスとして捉え、補助金を賢く活用して力強く乗りこなしていく。その一歩を踏み出すことが、貴社の5年後、10年後の未来を大きく左右するかもしれません。
おすすめ関連記事
→SHIFT事業とは?日本の脱炭素化を牽引する制度
参考文献
- 経済産業省 資源エネルギー庁「省エネルギー関連情報」
- 中小企業庁「ものづくり補助金総合サイト」
- 中小企業庁「事業再構築補助金」
- 環境省「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)」
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)ウェブサイト
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構「jGrants(電子申請システム)」