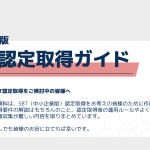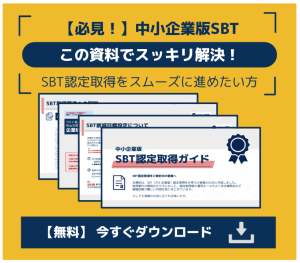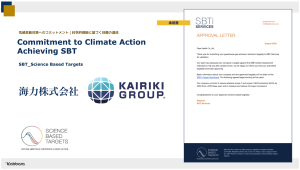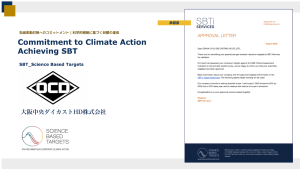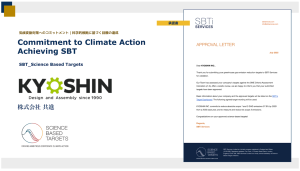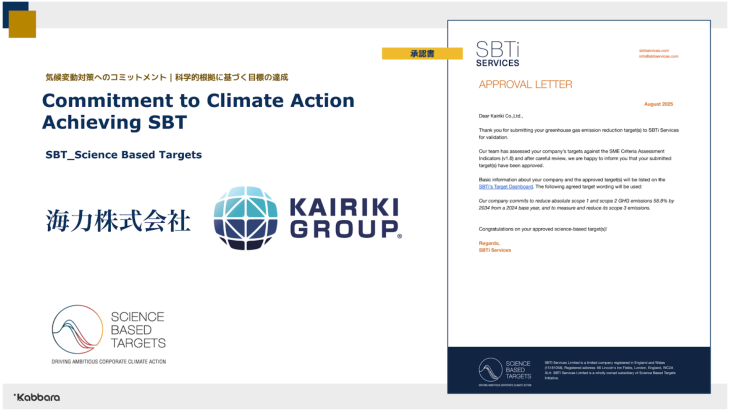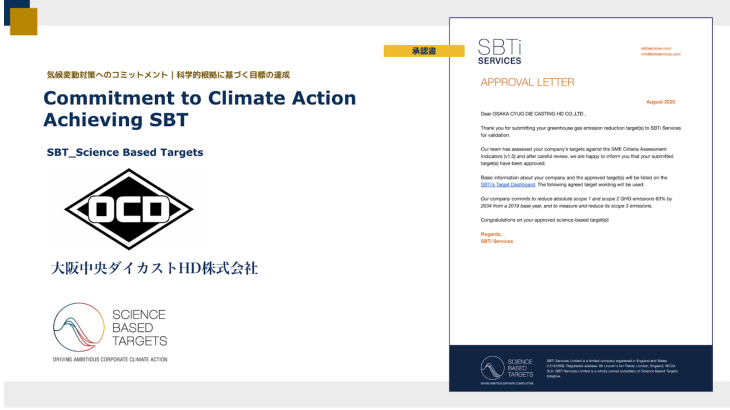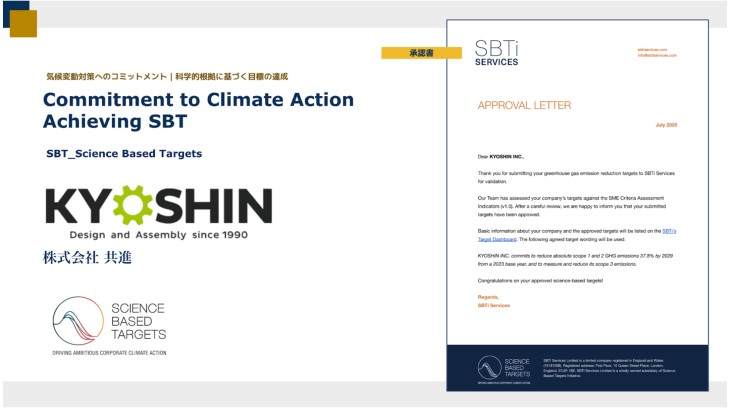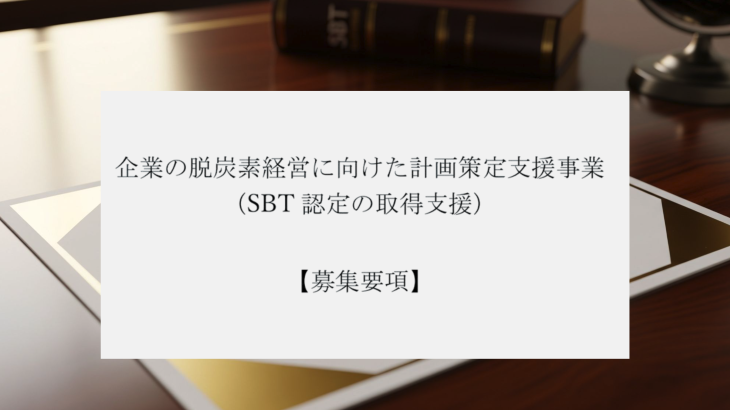はじめに
地球温暖化は、私たちの社会や経済に深刻な影響を与える喫緊の課題であり、企業には温室効果ガス排出量の削減が強く求められています。その有効な手段として注目されているのが、科学的根拠に基づいた目標設定(Science Based Targets:SBT)です。SBTはパリ協定の目標達成を念頭に、企業が排出量削減目標を設定するための枠組みとなります。
近年、取引先からの要請などをきっかけに、中小企業でもSBT取得の動きが広まっています。従来のSBTと比較して、中小企業版SBTは手続きが簡略化されており、より取り組みやすくなっています。
本記事では、SBT取得を任された担当者の方に向けて、申請に必要な排出源の4つの区分を分かりやすく解説します。排出量の把握には、Scope1、Scope2、Scope3という国際的な基準がありますが、今回はScope1に焦点を当て、温室効果ガス排出源を4つの区分に分類して解説していきます。
サマリー
- この記事では、中小企業版SBT認定取得に必要な排出源の4つの区分について、Scope1に焦点を当てて解説しています。
- 申請に必要な排出源の4つの区分とは、固定燃焼、移動燃焼、漏洩排出、プロセス排出です。
- それぞれの排出源、算定方法、排出量削減のための対策例などが紹介されています。
- 企業は自社の排出量を正確に把握し、排出量削減に向けた取り組みを進めることが重要です。
SBT認定取得サービス
→SBT認定取得はプロにお任せ!取得率100%の専門家チームが最短ルートで導きます
- 基準年における「固定(定常)燃焼」に伴う排出量( tCO2e単位)を記入してください。
- 基準年における「移動燃焼」に関連する排出量(tCO2e単位)を記入してください。
- 基準年における「漏えい」排出量( tCO2e単位)を記入してください。
- 基準年における「プロセス」排出量(tCO2e単位)を記入してください。
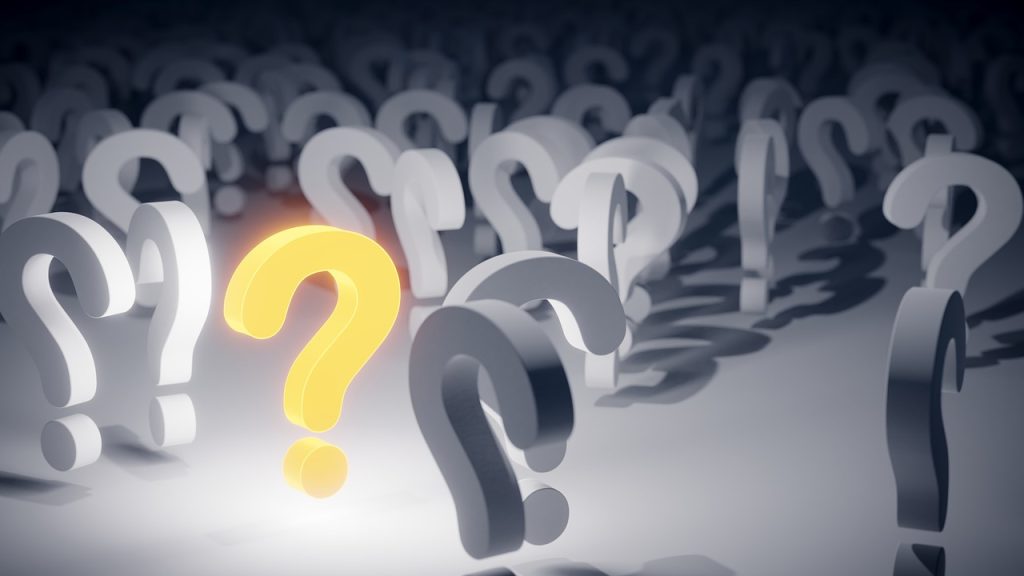
中小企業版SBTターゲット検証項目では、上記4つの区分による排出量の整理が求められています。それぞれの排出源と排出量の算定方法について、さらに詳しく見ていきましょう。
1. 固定(定常)燃焼:エネルギーを生み出す設備からの排出
固定燃焼とは、燃料を燃焼させてエネルギーを得る際に発生する温室効果ガスの排出です。工場やオフィスなどで、固定された場所で燃料を燃焼させる設備からの排出が該当します。

主な排出源
ボイラー:暖房や給湯、製造プロセスに利用されるボイラー。燃料の種類は、重油、軽油、都市ガス、LPGなど様々です。
例)事務所の暖房用ボイラー、工場の蒸気発生用ボイラー
発電機:電力を自社で発電するための設備。非常用発電機なども含まれます。
例)工場の自家発電設備、病院の非常用発電機
焼却炉: 廃棄物を焼却処理する際に発生する排出。
例)産業廃棄物焼却炉、医療廃棄物焼却炉
乾燥炉: 製品を乾燥させるために利用される炉。
例)食品工場の乾燥炉、窯業工場の乾燥炉
厨房設備: 業務用厨房で使用するガスコンロやオーブンなど。
例)飲食店の厨房設備、社員食堂の厨房設備
暖房設備: 石油ストーブやガスファンヒーターなど、暖房に使用する設備。
例)オフィスの暖房設備、店舗の暖房設備
排出量の算定方法
固定燃焼からの排出量は、以下の式で算定します。
排出量 = 燃料使用量 × 排出係数
■燃料使用量: 実際に使用した燃料の量を、種類ごとに正確に把握します。検針票や納品書などを参考にしましょう。
■排出係数: 燃料の種類や燃焼効率によって異なる係数です。環境省や経済産業省などが公表している排出係数データベースなどを活用し、適切な排出係数を使用します。
排出量削減のための対策例
▼高効率ボイラーへの更新:
最新の省エネルギー型のボイラーに更新することで、燃料消費量を削減できます。
▼燃料の種類の変更:
重油から天然ガスなど、より排出係数の低い燃料への転換を検討します。
▼廃熱利用システムの導入:
工場などで発生する廃熱を回収し、暖房や給湯に再利用することで、エネルギー消費量を削減できます。
▼設備の稼働率の適正化:
設備の稼働時間を調整したり、複数台の設備を効率的に運用することで、無駄なエネルギー消費を抑えられます。
▼断熱材の設置による熱損失の削減:
配管やダクトなどに断熱材を設置することで、熱の損失を減らし、エネルギー効率を高められます。
▼定期的なメンテナンス:
設備の定期的な点検や清掃を行うことで、燃焼効率を維持し、排出量を削減できます。
2. 移動燃焼:移動を伴う設備からの排出
移動燃焼とは、移動するものを動かすために燃料を燃焼させて発生する温室効果ガスの排出です。自動車、トラック、フォークリフトなど、移動手段となる設備からの排出が該当します。

主な排出源
社用車: 業務で使用する自家用車や営業車など。ガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車など、様々な車種があります。
例)営業担当者の社用車、配送用のトラック
トラック: 荷物を運搬するためのトラック。大型トラック、中型トラック、小型トラックなど、積載量によって様々な種類があります。
例)物流会社のトラック、建設会社のダンプカー
フォークリフト: 倉庫や工場などで荷物を運搬するためのフォークリフト。
例)倉庫内の荷役作業、工場内の搬送作業
建設機械: 建設現場で使用するブルドーザー、ショベルカー、クレーン車など。
例)道路工事、ビル建設
航空機: 出張や輸送などで利用する航空機。国内線、国際線など、様々な路線があります。
例)海外出張、商品の空輸
船舶: 海上輸送などで利用する船舶。貨物船、タンカーなど、様々な種類があります。
例)原材料の輸入、製品の輸出
排出量の算定方法
移動燃焼からの排出量は、以下の式で算定します。
排出量 = 燃料使用量 × 排出係数
■燃料使用量: 実際に使用した燃料の量を、種類ごとに正確に把握します。給油記録や燃料購入記録などを参考にしましょう。
■排出係数: 燃料の種類やエンジンの種類、走行距離などによって異なる係数です。環境省や経済産業省などが公表している排出係数データベースなどを活用し、適切な排出係数を使用します。
排出量削減のための対策例
▼エコドライブの推進:
急発進・急ブレーキを避け、アイドリングストップを心がけるなど、エコドライブを推進することで、燃料消費量を削減できます。
▼ハイブリッド車や電気自動車の導入:
燃費の良いハイブリッド車や電気自動車を導入することで、燃料消費量を削減できます。
▼運送ルートの最適化:
配送ルートを効率化することで、走行距離を減らし、燃料消費量を削減できます。
▼公共交通機関の利用:
社員の出張や通勤に公共交通機関を利用することで、社用車の使用を減らせます。
▼Web会議の活用による出張の削減:
Web会議システムを活用することで、出張回数を減らし、移動に伴う排出量を削減できます。
▼積載効率の向上:
トラックなどの積載効率を上げることで、輸送回数を減らし、燃料消費量を削減できます。
3. プロセス排出:製品の製造・使用に伴う排出
プロセス排出とは、製造プロセスや製品の使用に伴い発生する温室効果ガスの排出です。化学反応、溶剤の使用、製品の製造や使用に直接関わる工程からの排出が該当します。

主な排出源
化学製品の製造: 化学反応を利用した製品の製造過程で発生する排出。
例)プラスチック製品、合成繊維、医薬品
半導体製造: 半導体の製造過程で使用する特殊なガスなどからの排出。
例)フッ素化合物、窒素酸化物
鉄鋼製造: 鉄鋼を製造する過程で発生する排出。
例)二酸化炭素、メタン
セメント製造: セメントを製造する過程で発生する排出。
例)二酸化炭素
溶剤の使用: 塗装や洗浄などに使用する溶剤からの排出。
例)トルエン、キシレン
排出量の算定方法
プロセス排出の排出量は、排出源の種類や規模、使用される原料や材料などによって異なります。そのため、排出量の算定には、専門的な知識や技術が必要となる場合があります。環境省や業界団体などが公表している排出係数や算定方法などを参考に、適切な算定方法を採用しましょう。
排出量削減のための対策例
▼プロセス改善による排出量の削減:
製造プロセスを改善することで、排出量を削減できます。例えば、工程の簡略化、設備の効率化、廃棄物の削減などが挙げられます。
▼排出量の少ない原料や材料への代替:
排出量の少ない原料や材料を使用することで、製品の製造に伴う排出量を削減できます。
▼廃棄物の削減:
製造過程で発生する廃棄物を削減することで、廃棄物処理に伴う排出量を削減できます。
▼リサイクルの推進:
廃棄物をリサイクルすることで、資源の有効活用と排出量の削減につながります。
▼溶剤の回収・再利用:
使用済み溶剤を回収し、再利用することで、溶剤の使用量を削減できます。
4. 漏洩排出:冷媒などの漏洩による排出
漏洩排出とは、設備や機器からの冷媒やガスの漏洩によって発生する温室効果ガスの排出です。エアコン、冷凍庫、冷蔵ショーケースなど、冷媒を使用する設備からの排出が該当します。

主な排出源
エアコン: オフィスや店舗などで使用するエアコン。
例)業務用エアコン、家庭用エアコン
冷凍庫: 食品などを冷凍保存するための冷凍庫。
例)業務用冷凍庫、家庭用冷凍庫
冷蔵ショーケース: 商品を冷蔵保存するためのショーケース。
例)コンビニエンスストアの冷蔵ショーケース、スーパーマーケットの冷蔵ショーケース
冷却装置: 機械などを冷却するための冷却装置。
例)データセンターの冷却装置、工場の冷却装置
排出量の算定方法
漏洩排出の排出量は、漏洩量と冷媒の種類によって異なります。漏洩量の測定には、専門的な機器や技術が必要となる場合があります。環境省や業界団体などが公表している算定方法などを参考に、適切な算定方法を採用しましょう。
排出量削減のための対策例
▼設備の定期的な点検:
冷媒を使用する設備を定期的に点検し、漏洩箇所がないか確認します。
▼漏洩箇所の修理:
漏洩箇所が見つかった場合は、速やかに修理を行います。
▼冷媒の回収・再生:
設備を廃棄する際や冷媒を交換する際には、冷媒を適切に回収し、再生利用します。
▼漏洩検知システムの導入:
冷媒の漏洩を自動的に検知するシステムを導入することで、早期発見・早期対応が可能になります。
▼冷媒の種類の変更:
地球温暖化係数の低い冷媒への変更を検討します。
まとめ
中小企業版SBTを申請するためには、自社の温室効果ガス排出量を正確に把握することが重要です。そのためには、排出源を「固定燃焼」「移動燃焼」「プロセス排出」「漏洩排出」の4つの区分に分類し、それぞれの排出量を適切な算定方法を用いて計算する必要があります。
この記事では、4つの区分について、それぞれ詳しく解説しました。それぞれの区分の排出源や算定方法、排出量削減のための対策例などを参考に、自社の排出量削減に向けた取り組みを進めていきましょう。
SBT取得に向けた業務は、慣れないことも多く大変かと思いますが、着実に進めていきましょう。この記事が、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
参考文献
環境省「中小企業向けSBT導入ガイドブック」
経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」